中古車を事業用途で購入する場合、新車で購入した場合と同様に法定耐用年数に従って減価償却が必要となります。
通常、経費は支払った段階で一括計上するイメージがあるものの、固定資産の場合は減価償却により計上しなければなりません。逆に言えば、中古車であっても減価償却により経費計上できるのです。
では、具体的にどのように償却すれば良いのでしょうか?本記事では中古車の減価償却方法や注意点を徹底解説します。

URBAN GARAGEは、車のちょっとした違和感や不安にも親身に寄り添う“街のクルマ屋さん”。国家資格整備士が在籍し、エンジン・ブレーキ・電装系まで幅広く対応。わからないことがあれば何でも相談OK。専門的なこともわかりやすく丁寧にご説明します。「こんなことで相談していいのかな?」と思うことこそ大歓迎。あなたのカーライフを全力でサポートします!
URBAN GARAGE!

URBAN GARAGEは、車のちょっとした違和感や不安にも親身に寄り添う“街のクルマ屋さん”。国家資格整備士が在籍し、エンジン・ブレーキ・電装系まで幅広く対応。わからないことがあれば何でも相談OK。専門的なこともわかりやすく丁寧にご説明します。「こんなことで相談していいのかな?」と思うことこそ大歓迎。あなたのカーライフを全力でサポートします!
減価償却とは?

減価償却とは、減価償却の対象資産を取得する際にかかった金額を、一定の方法によって各年分の必要経費として配分するための手続きのことです。減価償却の対象となる資産には、事業などの業務に用いられる以下のものが該当します。
- 建物
- 建物附属設備
- 機械装置
- 器具備品
- 車両運搬具など
上記については、一般的には時間が経過すればするほど価値が減っていくものです。車の場合も状態の変化やモデルチェンジなどによって年数が経過するほど価値が下がっていきます。
例えば、200万円の自動車を経費で購入する場合、毎年30万円ずつ6年にわたって減価償却費します。
以上のように、購入した年にすべてを経費とするわけではなく、何年かにわたって分割して経費とするのが減価償却です。
中古車で減価償却する場合の方法
中古車を購入した際に減価償却する場合、以下2つの計算方法から選択する必要があります。
- 定額法
- 定率法
各計算方法にはメリットとデメリットがあり、最適な方法を選択できるかが重要です。ここでは、定額法と定率法それぞれの特徴などを紹介します。
定額法
定額法とは、毎年一定の額で減価償却する方法となります。車の取得価額に対して、定額法の償却率をかけて計算する方法です。償却率は、車の取得年数や耐用年数によって異なる特徴があります。
車の購入代金を減価償却したい場合、1年ごとではなく1年分を12分割してひと月ごとに計上するのが特徴です。
定額法は毎年の償却費が一定で理解しやすく、計算が容易な方法です。
例えば、96万円で購入した中古車の耐用年数が4年(48か月)の場合は、年間の減価償却費は24万円、月額では12,000円を計上します。定額法では、年数が経過して価値が下がったとしても、一定の償却費が計上されるのが特徴です。
これにより、年数が経過すればするほど価値に対する償却費の比率が高くなります。また、計算が容易であり理解しやすいメリットがあります。一方、初年度の節税効果が低い点は大きなデメリットです。
定率法
定率法とは、ものの残りの価値に対して一定割合の金額を計上する方法です。償却費は償却率により算出され、経年によって物品の価値が下がっても一定割合の金額を計上します。償却率は耐用年数ごとに決められています。
定率法の場合、購入した直後の資産価値が高い状態では償却費が多く、経年により価値が下がると償却費も減るのが特徴です。定率法は、資金回収が早く初年度の節税効果が高いメリットがあります。
一方、計算が複雑であり間違いやすい点には注意が必要です。
新車と中古車の減価償却の違い

車を購入した際、新車か中古車かによって減価償却に違いが生じます。ここでは、新車と中古車の減価償却の違いについて解説します。
新車の減価償却
新車で自動車を購入した場合でも、固定資産の購入にかかった費用を一括で費用として計上できません。毎期、減価償却費を計算した上で固定資産の法定耐用年数内で按分して、費用計上する必要があります。
固定資産の法定耐用年数は、国税庁によって定められていて普通自動車で新車の場合の定耐用年数は6年です。
中古車の減価償却
中古車の減価償却も、新車と同じく固定資産の取得扱いとなり購入にかかった費用は一括で費用として計上できません。減価償却によって、毎期の費用を計上する形が取られます。
ただし、中古車として購入した際の固定資産の法定耐用年数については、新車の場合よりも短くなるのが一般的です。よって、1年で経費として計上できる金額が大きくなる違いがあります。
車両の耐用年数
新車で車を購入した場合の法定耐用年数は、以下のように普通自動車と軽自動車で異なります。
| 種類 | 法定耐用年数 |
| 普通自動車 | 6年 |
| 軽自動車 | 4年 |
中古車として購入した場合、法定耐用年数は以下の計算方法により算出します。
| パターン | 法定耐用年数の計算方法 |
| 既に法定耐用年数の期間を過ぎた状態の場合 | 中古車の法定耐用年数の20%に相当する年数(法定耐用年数×20%) |
| 法定耐用年数の期間内である場合 | (法定耐用年数から利用した年数を差し引いた年数)+(利用した年数×20%) |
なお、算出時に発生した端数の箇所は切り捨てて計算することになります。また、算出したら2年未満になってしまうケースでは、法定耐用年数を2年とみなすルールとなっています。

URBAN GARAGEは、車のちょっとした違和感や不安にも親身に寄り添う“街のクルマ屋さん”。国家資格整備士が在籍し、エンジン・ブレーキ・電装系まで幅広く対応。わからないことがあれば何でも相談OK。専門的なこともわかりやすく丁寧にご説明します。「こんなことで相談していいのかな?」と思うことこそ大歓迎。あなたのカーライフを全力でサポートします!
URBAN GARAGE!

URBAN GARAGEは、車のちょっとした違和感や不安にも親身に寄り添う“街のクルマ屋さん”。国家資格整備士が在籍し、エンジン・ブレーキ・電装系まで幅広く対応。わからないことがあれば何でも相談OK。専門的なこともわかりやすく丁寧にご説明します。「こんなことで相談していいのかな?」と思うことこそ大歓迎。あなたのカーライフを全力でサポートします!
経過年数による耐用年数一覧

耐用年数は、中古車の方が新車と比較して短くなります。一方、減価償却の観点で言えば耐用年数が短いほど経費を多く計上できる計算となります。
以上の関係から、経過月数による耐用年数を把握しておくことは重要です。ここでは、経過年数による耐用年数一覧を種類別に紹介するので、ぜひ参考にしてください。
軽自動車の場合
軽自動車を新車で購入した際の法定耐用年数は、4年に設定されています。中古車の耐用年数の推移をまとめると、以下となります。
| 新車登録からの経過月数 | 法定耐用年数 |
| 1ヶ月~15ヶ月 | 3年 |
| 16ヶ月以上 | 2年 |
例えば、16ヶ月(=1.33年)経過している中古車の耐用年数は、以下で算出できます。
耐用年数 = (4-1.33)+(1.33×0.2) = 2.936
1年未満は切り捨て扱いとなるため、耐用年数は2年になる形です。もし早期に経費計上したい場合、新規登録から16ヶ月経過している軽自動車の購入がおすすめです。
普通車の場合
普通車を新車として購入した場合の耐用年数は、6年となります。中古車を購入した場合で新車登録から経過した月数別の耐用年数の推移は、以下のようになります。
| 新車登録からの経過月数 | 法定耐用年数 |
| 1ヶ月~15ヶ月 | 5年 |
| 16ヶ月~30ヶ月 | 4年 |
| 31ヶ月~45ヶ月 | 3年 |
| 46ヶ月以上 | 2年 |
新車登録から46ヶ月(=3.83年)経過下地点での耐用年数は、以下の計算で算出します。
耐用年数 = (6-3.83)+(3.83×0.2) = 2.936
1年未満は切り捨てて計算るルールとなっており、耐用年数は2年となります。
普通自動車の場合、新規登録から3年経過したタイミングで車検を受けなければなりません。車検を受けないで中古車として売却するケースが多く、またワンオーナー車が大半であり、程度の良い中古車を入手できる可能性が高いです。また、2回目の車検を受ける5年前後の場合は耐用年数が2年となり、早期に減価償却が可能となります。
貨物自動車の場合
事業用車両として、貨物自動車を中古車として購入したい場合もあるでしょう。貨物自動車の場合の法定耐用年数は、以下のとおりです。
| 貨物自動車種類 | 法定耐用年数 |
| 一般用のダンプ式貨物自動車 | 4年 |
| その他貨物自動車 | 5年 |
| 運送事業といった業務用の2トン以下の貨物トラック | 3年 |
| 総排気量3リットル以上の大型トラック | 5年 |
| その他のトラック | 4年 |
一般的に、事業用に使用する車両は使用頻度が高い傾向があります。これにより、耐用年数が短くなる場合が多いのです。
また、貨物自動車は整備点検などメンテナンスの頻度が多くなる関係上、その経費も考慮すると良いでしょう。貨物自動車の車検の有効期限をまとめると、以下のようになります。
| 区分 | 車検頻度 |
| 事業用で車両総重量8t未満 | 初回が2年、2回目以降は1年 |
| 車両総重量が8t以上 | 一律で1年 |
| 事業用の軽自動車 | 一律で2年 |
上記から、軽自動車を除くと基本的に1年であることが分かります。
短期間で減価償却したい場合の耐用年数

減価償却を主体として考える場合、耐用年数が短くなるタイミングで購入する方がお得です。耐用年数ばかりに着目して、状態の悪い中古車を購入するのは本末転倒です。
耐用年数が短い方が良いというわけではなく、保有していたオーナーの使用状況により状態は異なります。以上から、経過月数を念頭に置きつつ、状態の良い中古車を選定するのがおすすめです。
一般的に耐用年数と車の状態の両方のバランスが良い、狙い目の経過月数は以下のとおりです。
| 種類 | 狙い目の経過月数 |
| 軽自動車 | 16ヶ月 |
| 普通乗用車 | 16ヶ月・31ヶ月・46ヶ月 |
上記のタイミングで耐用年数が少なくなり、減価償却する際に計上できる金額を高くできます。
また、車の平均使用年数は年々長期化しており、一般財団法人自動車検査登録情報協会が公表している、平成31年3月末の平均使用年数によれば、以下の年月となっています。
| 種類 | 平均使用年数 |
| 普通乗用車 | 13.26年 |
| 貨物車 | 15.17年 |
車の性能やメンテナンス技術の向上が要因となっているとみられています。メンテナンスが行き届いている車の場合、耐用年数を超えても問題なく乗り続けることが可能です。車のコンディションをよく確認したうえで、税金面も考えてバランスが良い車を購入しましょう。
中古車の減価償却費計算例

ここでは、中古車の減価償却費の計算例を、定額法と定率法それぞれに分けて紹介します。以下の条件を用いて、定額法と定率法それぞれの条件を適用します。
以下のケース別に詳しく計算方法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
ケース1:3年落ちで取得価額200万円の中古普通自動車を購入した場合
ケース2:2年落ちで取得価額200万円の中古軽自動車を購入した場合
定額法の場合
最初に、耐用年数があとどの程度残っているかを以下の式で算出します。
ケース1:耐用年数 = 6 – 3 +(3 × 0.2) = 3.6年
ケース2:耐用年数 = 4 – 2 +(2 × 0.2) = 2.4年
小数点以下は切り捨て処理となるため、耐用年数は3年と2年になります。定額法の場合、「取得価額×定額法の償却率」で減価償却額を算出できます。
なお、売却率は耐用年数に応じて以下に該当する率を適用します。
| 耐用年数 | 定額法償却率 |
|---|---|
| 2 | 0.500 |
| 3 | 0.334 |
| 4 | 0.250 |
| 5 | 0.200 |
| 6 | 0.167 |
| 7 | 0.143 |
| 8 | 0.125 |
| 9 | 0.112 |
| 10 | 0.100 |
| 11 | 0.091 |
| 12 | 0.084 |
| 13 | 0.077 |
| 14 | 0.072 |
| 15 | 0.067 |
耐用年数が3年は定額法償却率は「0.334」を、2年の場合「0.500」を適用します。上記から、各ケース別で計算すると以下となります。
ケース1の減価償却費 = 200万円 × 0.334 = 668,000円
ケース2の減価償却費 = 200万円 × 0.500 = 1,000,000円
以上の金額から、1年あたりの減価償却額は以下のようになります。
ケース1 = 668,000 ÷ 3 = 222,666円
ケース2 = 1,000,000 ÷ 2 = 500,000円
定率法の場合
定額法と同様に、最初に耐用年数を算出しておく必要があります。計算式は同じであり、今回の例では各々3年と2年となります。
定率法の場合、「未償却残高 × 定率法の償却率」で計算することになり、それぞれの年度で以下を計上可能です。
【ケース1】
- 1年目:2,000,000円 × 0.667 = 1,334,600円
- 2年目:(2,000,000円 – 1,334,600円) × 0.667 = 443,821円(小数点以下切り捨て)
- 3年目:(2,000,000円 – 1,600,399円) × 0.667 = 147,793円(小数点以下切り捨て)
【ケース2】
- 1年目:2,000,000円 × 1 = 2,000,000円
- 2年目:(2,000,000円 – 2,000,000円) × 1 = 0円
以上のように、1年目に高い金額を計上できる一方、2年目以降は計上できる金額が大きく変動します。
また、ケース2のように1年目で一括で経費計上するケースもあります。

URBAN GARAGEは、車のちょっとした違和感や不安にも親身に寄り添う“街のクルマ屋さん”。国家資格整備士が在籍し、エンジン・ブレーキ・電装系まで幅広く対応。わからないことがあれば何でも相談OK。専門的なこともわかりやすく丁寧にご説明します。「こんなことで相談していいのかな?」と思うことこそ大歓迎。あなたのカーライフを全力でサポートします!
URBAN GARAGE!

URBAN GARAGEは、車のちょっとした違和感や不安にも親身に寄り添う“街のクルマ屋さん”。国家資格整備士が在籍し、エンジン・ブレーキ・電装系まで幅広く対応。わからないことがあれば何でも相談OK。専門的なこともわかりやすく丁寧にご説明します。「こんなことで相談していいのかな?」と思うことこそ大歓迎。あなたのカーライフを全力でサポートします!
中古車で減価償却する際の注意点

中古車を購入して減価償却する場合、以下の点に注意して対応しましょう。
- 購入する車種に注意する
- 個人事業主の場合は経費計上で家事按分が必要となる
- 車の改造や修理により耐用年数が長くなる
- ローン返済部分は利息のみ経費計上できる
- カーリースなら全額経費に計上できる
各注意点の詳細を解説するので、ぜひ参考にしてください。
購入する車種に注意する
減価償却する際、趣味性や嗜好性の高い車の場合は税務調査が行われた際に税務署から指摘される可能性があります。
例えば、規模の小さな会社で事務用品の販売を手掛けている会社が、高級SUVを配達用に使用していると違和感を覚えるものです。
事業用車両はあくまでも事業で使用されているものであり、プライベート目的で購入したものは該当しません。
購入した車が事業にどのように寄与しているのか、業務とプライベートで各々どの割合で使用されているのかを説明する必要があります。
個人事業主の場合は経費計上で家事按分が必要となる
個人事業主が車を保有している場合、経費計上で家事按分する必要があります。家事按分とは、事業とプライベートを兼ねている支出の場合、事業分だけを経費計上するため割合で分ける計算方法のことです。
例えば、自宅の一角を用いて事業を行なっている場合、光熱費はトータルの金額ではなく事業で使用する部屋の分だけが経費扱いにできます。車の場合も、総使用時間に対して事業目的でどのくらいの割合で使用したかを算出し、家事按分しなければなりません。
プライベートで使用するケースが多い車両を、家事按分せず全額計上すると税務調査時に指摘されるため注意しましょう。
車の改造や修理により耐用年数が長くなる
車を改造したり修理したりする場合、対応年数が長くなる特徴があります。
具体的には、以下の両方を満たす場合に新車と同様の扱いとなり、中古車に対して適用する耐用年数をそのまま利用できません。
- 改造や改良によって中古車の機能が高まって耐用年数を伸ばすものである
- 支出金額が中古車と同じものを新車購入価格の50%を超えている
上記に該当する場合、新車の法定耐用年数を適用しなければなりません。
ローン返済部分は利息のみ経費計上できる
ローンで購入した中古車であっても、事業用途として購入したものは全額を経費として計上可能です。
基本的に、経費として認められる・認められない車種の区分けはありません。車両本体価格を含めた返済額は経費計上できないものの、支払利息について経費計上を行うことが可能です。
ここで注意したいのが、支払利息のみ経費計上できることを車両本体価格が経費計上できないと捉え、ローンは車両価格を経費で計上できないと誤った解釈をしてしまうことです。
毎月支払うローン金額の中で、元本は車両代金の返済であり、別の経費計上を行うことになり月々のローン金額は支払利息分を経費で計上することになります。
要するに、ローンを返済する際は月々支払うローンの元本は減価償却でき、支払利息は経費として計上する二本立ての対応が必要となるのです。
カーリースなら全額経費に計上できる
中古車ではなくカーリースを利用すれば、リース料を全額経費として計上可能です。一般的なカーリースの場合、リース料金にメンテナンス料や税金も含まれているため、節税効果が高いメリットがあります。
さらに、所有者がリース会社であるため、固定資産税を計上する必要がなく、減価償却の計算などの手間も省けます。
まとめ
中古車を購入する場合でも、減価償却によって経費を計上できます。経費を適切に計上できれば、高い節税効果が期待できます。
中古車の場合、購入するタイミングなどによって定額法または定率法のどちらを選択するかにより節税効果が異なるのです。本記事で紹介した内容を参考に、適切な方法を選択して節税対策を行いましょう。

URBAN GARAGEは、車のちょっとした違和感や不安にも親身に寄り添う“街のクルマ屋さん”。国家資格整備士が在籍し、エンジン・ブレーキ・電装系まで幅広く対応。わからないことがあれば何でも相談OK。専門的なこともわかりやすく丁寧にご説明します。「こんなことで相談していいのかな?」と思うことこそ大歓迎。あなたのカーライフを全力でサポートします!
URBAN GARAGE!

URBAN GARAGEは、車のちょっとした違和感や不安にも親身に寄り添う“街のクルマ屋さん”。国家資格整備士が在籍し、エンジン・ブレーキ・電装系まで幅広く対応。わからないことがあれば何でも相談OK。専門的なこともわかりやすく丁寧にご説明します。「こんなことで相談していいのかな?」と思うことこそ大歓迎。あなたのカーライフを全力でサポートします!




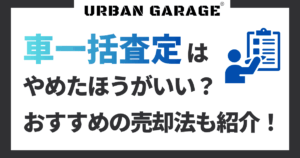
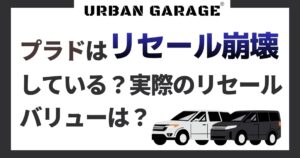





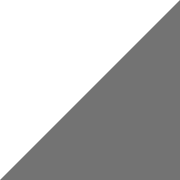



コメント